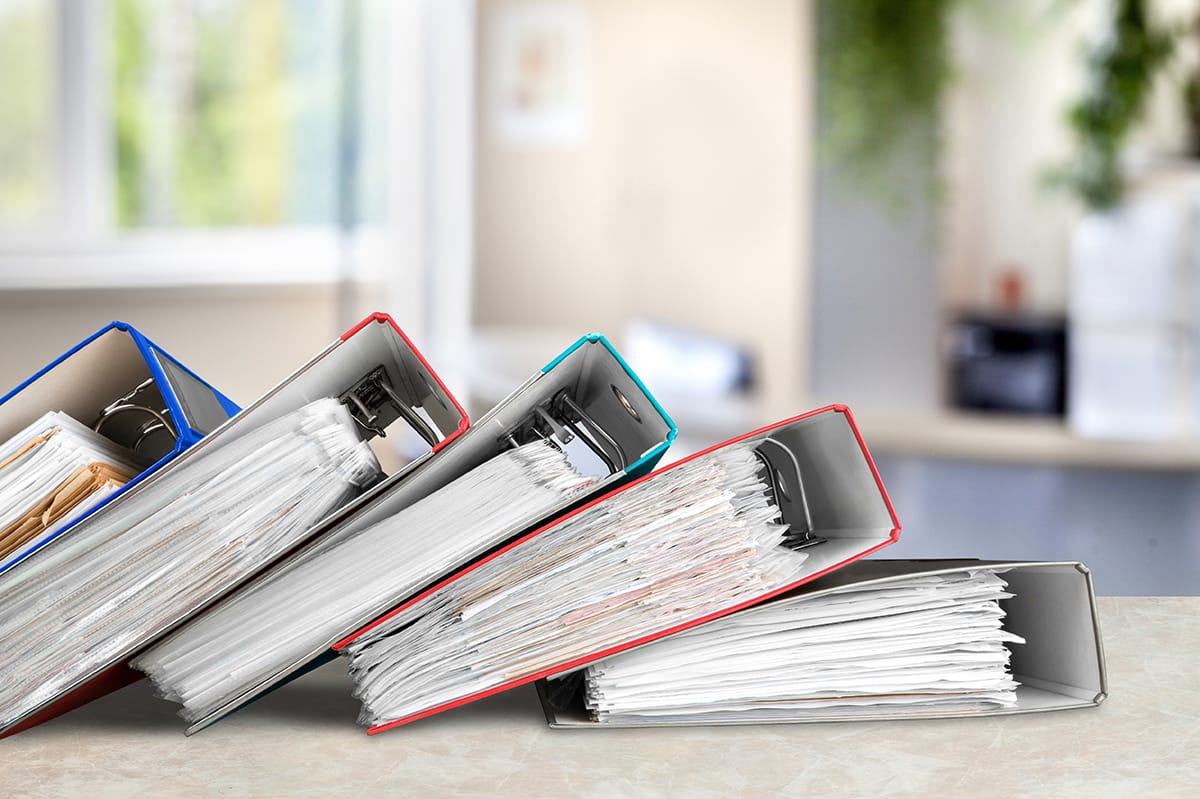「法定保存文書(法律で保存が定められている文書)にはどういった文書が該当するのか」「保存期間はどのくらいなのか」に悩まされている方は多いのではないでしょうか。この記事では最新の法定保存文書を保存期間ごとに一覧にしています。社内の文書を保存するときの参考に利用してください。
法定保存文書とは?
法定保存文書とは、法律で保存が定められている書類のことです。法人の企業で発生する書類の多くは法定保存文書にあたります。法定保存文書は、定められた保存年数を守って保存しておかなければなりません。特に、経理関係の文書を保存していないと、監査の際に不利になりやすいと言えます。保存期間が満了する前に誤って廃棄したり、紛失したりしないようしっかりと保存しておきましょう。
法定保存文書の保存期間は文書によってそれぞれ異なるため、すべての文書の保存期間を控えておく必要があります。次の項で法定保存文書を一覧にしてみたので、文書保存にお役立てください。
<最新>法定保存文書の保存期間一覧
保存が必要な法定保存文書一覧は以下になります(更新:2023.1.24)
経理・税務関係書類の保存期間
| 保存期間 | 文書名 | 起算日 |
|---|---|---|
| 10年 | 計算書類および附属明細書 (貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表) | 株主総会の日 |
| 10年 | 会計帳簿および事業に関する重要書類 (総勘定元帳、各種補助簿、株式申込簿、株式割当簿、株式台帳、株式名義書換簿、配当簿、印鑑簿など) | 帳簿閉鎖の時 |
| 7年 | 取引に関する帳簿 (仕訳帳、現金出納帳、固定資産台帳、売掛帳、買掛帳など) | 事業年度の確定申告書の提出期限の翌日 |
| 7年 | 決算に関して作成された書類 (上に挙げた、10年保存が義務づけられている書類以外) | 事業年度の確定申告書の提出期限の翌日 |
| 7年 | 現金の収受、払出、預貯金の預入・引出に際して作成された取引証憑書類 (領収書、預金通帳、借用証、小切手・手形控、振込通知書など) | 事業年度の確定申告書の提出期限の翌日 |
| 7年 | 有価証券の取引に際して作成された証憑書類 (有価証券受渡計算書、有価証券預り証、売買報告書、社債申込書など) | 事業年度の確定申告書の提出期限の翌日 |
| 7年 | 取引証憑書類 (請求書、注文書、契約書、見積書、仕入伝票など) | 事業年度の確定申告書の提出期限の翌日 |
| 7年 | 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書、配偶者特別控除申告書、保険料控除申告書 | 提出期限の属する年の翌年1月10日の翌日 |
| 7年 | 給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書 | 提出期限の属する年の翌年1月10日の翌日 |
| 7年 | 源泉徴収簿(賃金台帳) | 提出期限の属する年の翌年1月10日の翌日 |
| 7年 | 課税仕入等の税額の控除に係る帳簿、請求書等 (6年目以降は、帳簿または請求書等のいずれかを保存) | 確定申告期限の翌日 |
| 7年 | 資産の譲渡等、課税仕入、課税貨物の保税地域からの引取りに関する帳簿 | 閉鎖の日の属する課税期間の末日の翌日から2ヶ月後の日 |
| 5年 | 監査報告(本店備置き分。支店備置き分はその謄本を3年保存)(監査役設置会社等の場合) | 株主総会の1週間(取締役会設置会社は2週間)前の日 |
| 5年 | 会計参与が備え置くべき計算書類、附属明細書、会計参与報告(会計参与設置会社の場合。会計参与が定めた場所に備置き) | 株主総会の1週間(取締役会設置会社は2週間)前の日 |
| 5年 | 金融機関等が保存する非課税貯蓄申込書、非課税貯蓄申告書、非課税貯蓄限度額変更申告書、非課 税貯蓄異動申告書、非課税貯蓄勤務先異動申告書、非課税貯蓄廃止申告書などの写し | 申告書、退職等に関する通知書等の提出があった年の翌年 |
| 5年 | 金融機関等が保存する海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の国内 勤務申告書などの写し | 申告書、退職等に関する通知書等の提出があった年の翌年 |
| 5年 | 金融機関等が保存する退職等に関する通知書 | 申告書、退職等に関する通知書等の提出があった年の翌年 |
人事・労務関係書類の保存期間
| 保存期間 | 文書名 | 起算日 |
|---|---|---|
| 5年 | 従業員の身元保証書 | 作成日 |
| 5年 | 誓約書などの書類 | 作成日 |
| 5年 | 賃金その他労働関係の重要書類(労働時間を記録するタイムカード、残業命令書、残業報告書など) | 賃金支払期日 |
| 5年 | 労働者名簿 | 完結の日 |
| 5年 | 賃金台帳(国税通則法では7年保存を義務づけ) | 賃金支払期日 |
| 5年 | 雇入れ・解雇・退職に関する書類 | 完結の日 |
| 5年 | 災害補償に関する書類 | 災害補償の終わった日 |
| 5年 | じん肺健康診断記録、じん肺健康診断に係るエックス線写真 | 作成日 |
| 5年 | 一般健康診断個人票 | 作成日 |
| 5年 | 有機溶剤等健康診断個人票 | 作成日 |
| 5年 | 鉛健康診断個人票 | 作成日 |
| 5年 | 四アルキル鉛健康診断個人票 | 作成日 |
| 5年 | 特定化学物質健康診断個人票 ※クロム酸等は30年 | 作成日 |
| 5年 | 高気圧業務健康診断個人票 | 作成日 |
| 5年 | 高圧室内業務の減圧状況の記録 | 作成日 |
| 5年 | 線量当量率の測定の記録 | 作成日 |
| 5年 | 放射性物質の濃度測定の記録 | 作成日 |
| 5年 | 放射線事故に関する測定の記録 | 作成日 |
| 5年 | 安全委員会議事録 | 作成日 |
| 5年 | 衛生委員会議事録、安全衛生委員会議事録 | 作成日 |
| 5年 | 救護に関する訓練の記録 | 作成日 |
| 5年 | 危険・有害業務に従事するときの安全衛生のためのときの安全衛生のための特別教育の記録 | 作成日 |
| 4年 | 雇用保険の被保険者に関する書類(雇用保険被保険者資格取得等確認通知書、同転勤届受理通知書、 同資格喪失確認通知書{離職証明書の事業主控}など) | 完結の日 |
| 3年 | 企画業務型裁量労働制についての労使委員会の決議事項の記録 | 決議の有効期間中及びその満了後 |
| 3年 | 労使委員会議事録 | 開催日 |
| 3年 | 労災保険に関する書類 | 完結の日 |
| 3年 | 労働保険の徴収・納付等の関係書類 | 完結の日 |
| 3年 | 家内労働者帳簿 | 最後の記入をした日 |
| 3年 | 派遣元管理台帳 | 派遣終了日 |
| 3年 | 派遣先管理台帳 | 派遣終了日 |
| 3年 | 身体障害者等であることを明らかにすることができる書類(診断書など) | 最後の記入をした日 |
| 3年 | 家内労働に関する帳簿 | 最後の記入をした日 |
| 2年 | 雇用保険に関する書類 (雇用保険被保険者関係届出事務等代理人選任・解任届など。労働保険の保険料の徴収等に関する法律または同施行規則による書類は3年) | 完結の日 |
| 2年 | 健康保険・厚生年金保険に関する書類 (被保険者資格取得確認および標準報酬決定通知書、標準報酬改定通知書など) | 完結の日 |
総務・庶務関係書類の保存期間
| 保存期間 | 文書名 | 起算日 |
|---|---|---|
| 10年 | 株主総会議事録(本店備置き分。支店備置き分はその謄本を5年保存) | 株主総会の日 |
| 10年 | 取締役会議事録 | 株主総会の日 |
| 10年 | 監査役会議事録 | 株主総会の日 |
| 10年 | 委員会議事録(指名委員会、監査委員会、報酬委員会)事業報告(本店備置き分。支店備置き分はその謄本を3年保存)-事業年度の確定申告書の提出期限の翌日 | 作成日 |
| 10年 | 重要会議の記録 | 作成日 |
| 10年 | 満期または解約となった契約書 | 満期または解約の日 |
| 10年 | 製品の製造、加工、出荷、販売の記録(※民法では、20年が期限) | 製品の引渡し日 |
| 5年 | 事業報告(本店備置き分。支店備置き分はその謄本を3年保存) | 事業年度の確定申告書の提出期限の翌日 |
| 5年 | 有価証券届出書・有価証券報告書およびその添付書類、訂正届出(報告)書の写し | 提出した日 |
| 5年 | 産業廃棄物管理票(マニフェスト)の写し | 伝票の送付を受けた日もしくは送付した日 |
| 5年 | 産業廃棄物処理の委託契約書 | 契約の終了の日 |
| 3年 | 四半期報告書、半期報告書およびその訂正報告書の写し | 提出した日 |
| 1年 | 臨時報告書、自己株券買付状況報告書およびそれぞれの訂正報告書の写し | 提出した日 |
| 3ヶ月 | 株主総会の代理権を証明した文書 | 株主総会の日 |
| 3ヶ月 | 株主総会の議決権行使に関わる文書 | 株主総会の日 |
▼また、医療・建設関係の書類はこちらもご確認ください
オススメの法定保存文書の保存方法
法定保存文書の保存期間は把握できたでしょうか? オススメの法定保存文書の保存法は、「廃棄するタイミングが同じ文書」をまとめて保存することです。そうすることで、廃棄する際にダンボールやファイルごと廃棄することができ、作業の手間を省くことができます。廃棄する際に再度文書を整理して集めるようでは、二度手間になってしまいます。
▼具体的な保存方法についてはこちらの記事もご覧ください。
もし社内の文書保存スペースに悩んでいたり、廃棄のタイミングを逃しがちだったりするのであれば、書類保管サービスの利用もオススメです。文書保管サービスとは、セキュリティ対策された倉庫に文書を預けることのできるサービスです。社内の文書保存スペースがすっきりするだけではなく、WEB管理システムなどで廃棄するタイミングも確認することができるため、文書管理の手間を省くことができます。
キーペックスなら文書保管サービスだけでなく、文書の電子化サービスや廃棄サービスなど文書に関連するさまざまなサービスを行っているため、文書管理にお困りの方に、より効率の良い文書管理方法をご提案することができます。
文書管理のお悩みがある方は、是非一度キーペックスにご相談ください。